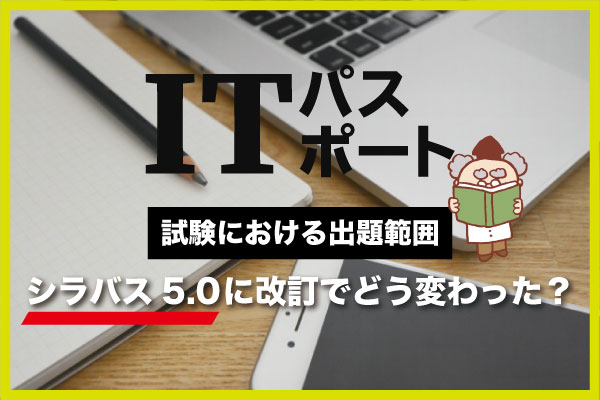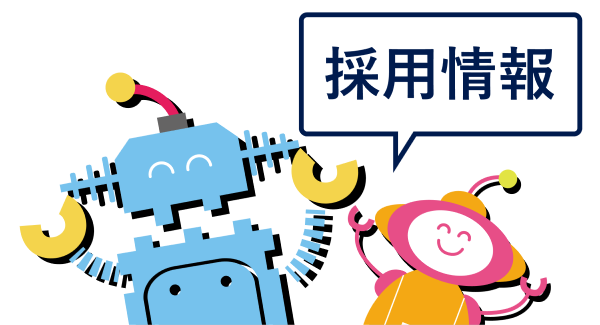公開日2021.06.09
最終更新日2022.10.04
シラバスが5.0に改訂されましたね!
2021年4月からはシラバスVer5.0より出題がされています。
これから試験を受けようとされている方は何がどのように変わったのか
気になるのではないでしょうか。
今回は、そもそもITパスポートってどんな資格?という点と
シラバス5.0になると何がかわるの?という一番大事な部分について
わかりやすく簡潔にお話していきたいと思います。
————————————————-
シラバス5.0への改訂から1年で、さらに6.0への改訂があります。
詳細はこちらの記事をチェック!
————————————————-
ITパスポート試験とは

ITパスポートとは?
ITパスポート試験は経済産業省が認定する国家資格でITに関する知識を証明するための資格、基礎的な知識を学習するための資格です。
IT業界に入ったら最低限、知識を身に着ける為に最初はこちらの資格を取っておくといいかもしれないですね。
IT業界以外に、事務職系に就いている方でもITに関するスキルを証明できるので持っていて損はない資格です。
こちらの資格は試験や会場や日時が限定されていません。
そのため提示された選択肢の中から自分の都合に合わせた場所・時間で受験することができて、ある程しっかりと試験対策もできて、都合の良いときに受験できるので社会人にとっては、とても嬉しいメリットになります!
~受験方法~
受験方法は公式サイトに登録します。その後、自分の身近な地域を選択し、その地域にある試験会場の中から希望の場所を選びます。
後は実施日時が選べるようになりますので希望の日時を選べば完了です。
受験方法や学習方法については別の記事でも紹介しております!
シラバスが4.6から5.0へ
そんなITパスポートが2021年4月からシラバスが4.6から5.0へと変わります。
4.6と5.0を比較したところ新しい用語が多くあり、数理、AIについても多くありました。
数値計算と数値解析の基礎知の問題も増え、機械学習やディープランニングなどのAI技術も追加されていました。
シラバス4.6ではあまりAIについての問題がありませんでしたので、これから受験を受ける方はAIの学習が必要になるかと思われます。
!注意!
- 新しい用語が増える
- 学習時間がかなり増える
- 練習する過去問が少ない
- 名称を知っているだけでは解けない問題が増える
- AIに関しての問題が多くなる
以下も必要なことになります。
- オプトイン
- 第三者提供
- 一般データ保護規則
- 消去権
- 仮名化
- 匿名化
- ブレーンストーミング
- 暗号資産
新しくなるシラバス5.0では、AIの問題が多くなるとお伝えしました。AIについて簡単に説明したいと思います。

人工知能 (artificial intelligence)の省略でAIと言います。
知的な行動を人間に変わって機械に行わせることで、人間にはできなかった高度な知識や作業判断をコンピューターがシステムで行えるようにしたものになります。
私たちの身近にあるものですと、
「指紋認識」、「音声認識」、「ロボット掃除機」などがあげられます。
また、自動車もAIに変わっていっていますね。
バスなど今は自動運転になっているものがあり、交通規制がかかっていない公道なら無人の自動運転が出来るそうです。
「音声認識」も
今じゃ専用の機械を家に設置し喋るだけで電気が着いたり消えたり、好きな音楽がすべての部屋で聴けたりと出来るようになっております。
これもAIだからできることです。
こうしてどんどん私たちの身近でAIが主流になっていき、そう遠くない未来すべての事がAIじゃないと出来ない事が当たり前になっていくのでないかと思いました。
他にも、
- 知的なゲームで対戦する
- 画像、人物を識別する認識
- 喋っている内容を認識する音声認識
- ロボット、自動車などの制御システム
- 質問応答システム(自然言語処理)
これらも当てはまります。
また、シラバス4.6から5.0で変わった用語の一つに「リスクアセスメント」という言葉があります。
~リスクアセスメントとは~
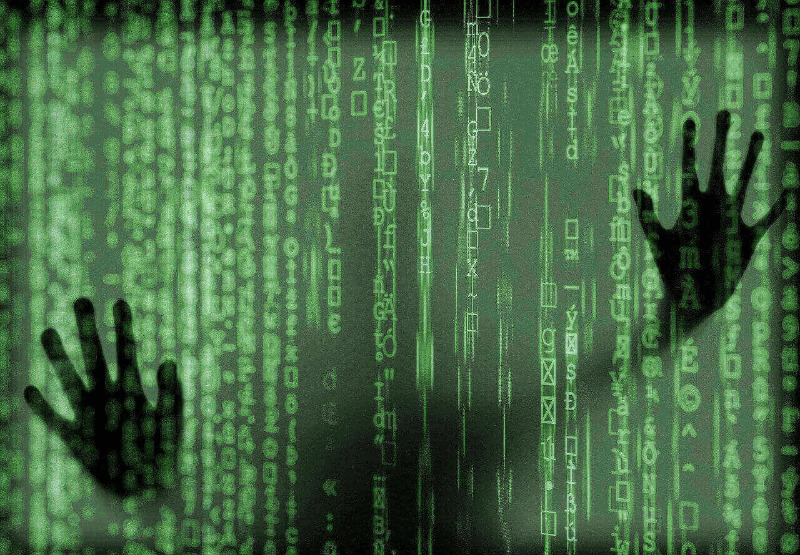
危険性や有害性の特定、リスクの見積り、優先度の設定、リスク低減措置の決定の一連の手順で、その結果に基づいて適切な労働災害防止対策を講じる必要がある。
これは【労働安全衛生法第28条の2】にて「危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づく措置」というのがあり、リスクアセスメントの結果に基づく措置の実施に取り組むことが努力義務とされており厚生労働省からも「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」というのが公表されています。
リスクアセスメント -3つのメリット-
- 職場でのリスクが明確になり、メンバー内で情報を共有できる
- 被害を最小限にできる
- 環境に応じてマニュアルを作成できる
メンバー内で共通の危機認識を持つことでリスク管理の意識を皆で共有でき、それにて万が一事故が発生しても対処することができます。
職場によって環境や設備は異なりますが、リスクアセスメントを使えば柔軟に対応が出来て状況に応じマニュアルを作成することが可能になります。
リスクはどこにでも潜んでいるもの、まだ起きてないからとそのままにしていると取り返しのつかないことが起こり大きなリスクとなって危機に陥ってしまいます。
そうしたことがないように、ここで必要になるのがリスクアセスメントになります。
ITパスポート試験も、最新技術やリスク、その施策にまで目を向けられている試験へと変化していっているように感じます。
~最後に~
シラバス5.0では新しい用語が増えますが、AIやリスクアセスメントに関しては私たちの身近にあり馴染み深いでのではないでしょうか。
最近ニュースや情報番組ででてくる用語もあったので、日々のニュースをチェックしていると覚えやすいかもしれません。
これからITパスポートを受験される方にこの記事が少しでもお役に立ちましたら嬉しいです。